私たちにできること(事業者編)
自社の温室効果ガス排出量の見える化
まずは、自社がどのくらい温室効果ガスを排出しているか把握しましょう。たとえばCO2であれば、「燃料の使用」や「電力の使用」など、活動ごとの排出量を計算・把握できるようになることが大事です。
温室効果ガス削減目標・取組計画の策定
いつまでに、どれほど排出量を削減するかの目標とその実現に向けた取組計画を立てましょう。
排出量削減のためにできることとしては、例えば、次のような取組があります。
再生可能エネルギーの使用
温室効果ガスの排出抑制効果がある設備の導入
(エネルギー効率の高い熱源や空調、屋上緑化など)
働き方改革の推進
(テレワークや自宅作業が可能となる態勢の整備やクールビズといった省エネの推進など)
物流の見直し
可能な限り、より短い距離の物流ルートやCO2排出量のより少ない輸送手段を選択する
その他
CO2排出量を踏まえた製品やサービスの値付け(いわゆるカーボンプライシング)を検討する

サプライチェーンと連携した取組推進
自社製品・サービスのライフサイクルにおける温室効果ガスを削減するには、サプライチェーンと協力して進める必要があります。
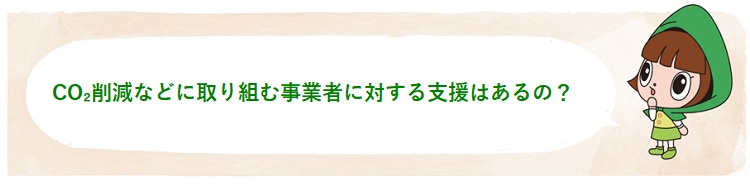
- A.CO2削減などに取り組む事業者に対して、補助金による支援があります。
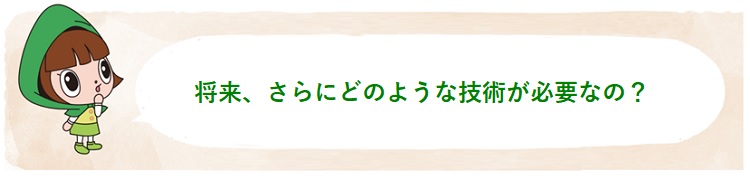
- A.今の技術だけでは温室効果ガスの排出量を十分に減らせない領域もあります。国際的な協力態勢のもと、新しい取組を進めていく必要があります。例えば、次のような技術開発が待たれます。
- 電力を蓄積する技術(バッテリー技術)の向上
- CO2を出さないエネルギー(例:風力、太陽光、水素などからつくる電力)に関する発電効率などの技術向上
- パワーグリッド(送配電)見直し—排出量が実質ゼロとなるようなセメントや鉄の生成プロセスの確立
- グリーンアンモニア(空気と水、再生可能エネルギーを用いて、CO2を排出しないプロセスで作られるアンモニア)などのクリーン燃料の実用化
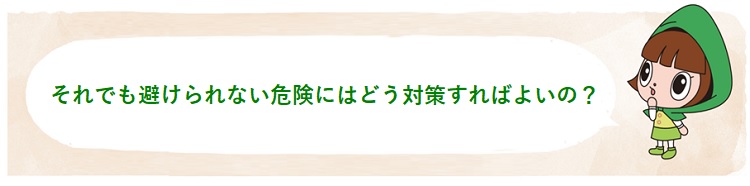
- A.年々激甚化する台風や豪雨などの災害への対策を行うことも重要です。 各地方自治体が出しているハザードマップを見て、事業活動している地域の危険を確認してください。また、自然災害発生時の休業リスク(事業中断リスク)などに備えて、事業者向け保険の加入もご検討ください。